眼鏡フレームの産地 福井県鯖江市(さばえし)
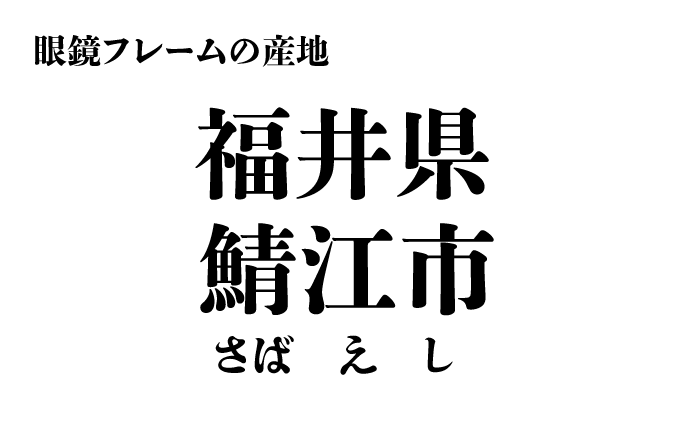
国産眼鏡フレームの約90%を生産している「福井県鯖江市(ふくいけん さばえし)」。
今、あなたが掛けている眼鏡が「made in Japan」なら、ほぼ鯖江市で製造されたメガネかもしれません。
今回は、なぜこの地方都市に眼鏡産業が根づき、世界的なブランドへと成長を遂げたのでしょうか。
その理由を歴史・地理・人材の観点から紐解いていきます。

※写真の高いビルは「めがねミュージアム」
1.眼鏡づくりの起点 ― 明治期の地場産業支援
鯖江で眼鏡産業が始まったのは、1905年(明治38年)。地元の小学校教員だった増永五左衛門が、冬場の副業として農家に眼鏡作りを提案・指導したのが起点です。雪深く、農業だけでは生活が成り立たなかった地域の事情と、増永の先見性がこの産業を生み出しました。
2.冬でもできる産業への需要
福井県嶺北地域は豪雪地帯であり、冬場は農作業が困難でした。そのため、屋内でできる手仕事が求められていました。眼鏡製造は細かい作業ながらも道具や場所をあまり取らず、農家の副業としてぴったりだったのです。

3.職人技とモノづくりの気質
鯖江の人々は、昔から丹念で器用な手仕事に長けており、漆器や繊維などの地場産業でもその技術力が発揮されてきました。眼鏡づくりにもその職人気質が活かされ、高品質な製品を生む土壌が整っていたといえます。

4. 一貫生産体制と技術革新
鯖江市では、材料の仕入れから設計・加工・仕上げまでを地域内で完結する分業体制が確立されました。これにより、品質と納期を両立した生産が可能になり、国内外のブランドからの信頼を得るようになります。さらに、チタンフレームの世界初の量産化など、技術革新をいち早く取り入れたことも競争力の強化に繋がりました。
鯖江で作られる眼鏡フレームは、一般的に200〜300もの工程を経て完成します。
各工程ごとに専門の工場や職人が分担し、パーツごと・工程ごとに高い技術を持ったスペシャリストが担当します。
具体的な分業の流れ(メタルフレームの場合)
- 企画・デザイン
- 金型製造(部品ごとの専用金型を作成)
- 部分品製造(リム、テンプル、ブリッジなどをプレス加工)
- 切削・研磨(パーツごとに精密な加工・磨き)
- 組み立て(ロウ付け、溶接、ネジ止めなど)
- 表面処理(メッキや七宝などの装飾・保護加工)
- 仕上げ研磨
- 最終検査
多くのメーカーは自社で上記の一部工程を担い、他の工程は専門業者に委託する形が主流です。特に中間加工業者や部品メーカーは、従業員3人以下の零細企業が多く、それぞれが特定の工程に専門特化しています。
鯖江市には眼鏡関連企業が約450社以上※あります。
※2016年 日本政策投資銀行資料より
5. 行政と企業の連携
地元自治体や商工会議所、企業が一体となって後継者育成やブランド戦略に取り組んでいる点も特徴です。海外市場開拓の支援など、産業の持続可能性を高める活動が現在も続けられています。
詳しくは、下記のホームページもご覧ください。
・福井・鯖江めがね案内総合サイト「Japan Glassese Factory」
・めがねミュージアム案内サイト「MEGANE MUSEUM」
・増永眼鏡ホームページ「MASUNAGA since1905」
おわりに
雪国・福井の一都市が、世界に誇る眼鏡産地へと成長した背景には、自然環境、地域の知恵、そして人の力がありました。鯖江の眼鏡は、単なる工業製品ではなく、地域の歴史と誇りが詰まった「文化」でもあるのです。
アイメガネでは、全店で職人たちの歴史と誇りが詰まった鯖江産の国産メガネフレームを多数取り扱っています。
また、一部店舗で国産ブランドフェア「福井鯖江展」を開催しています。
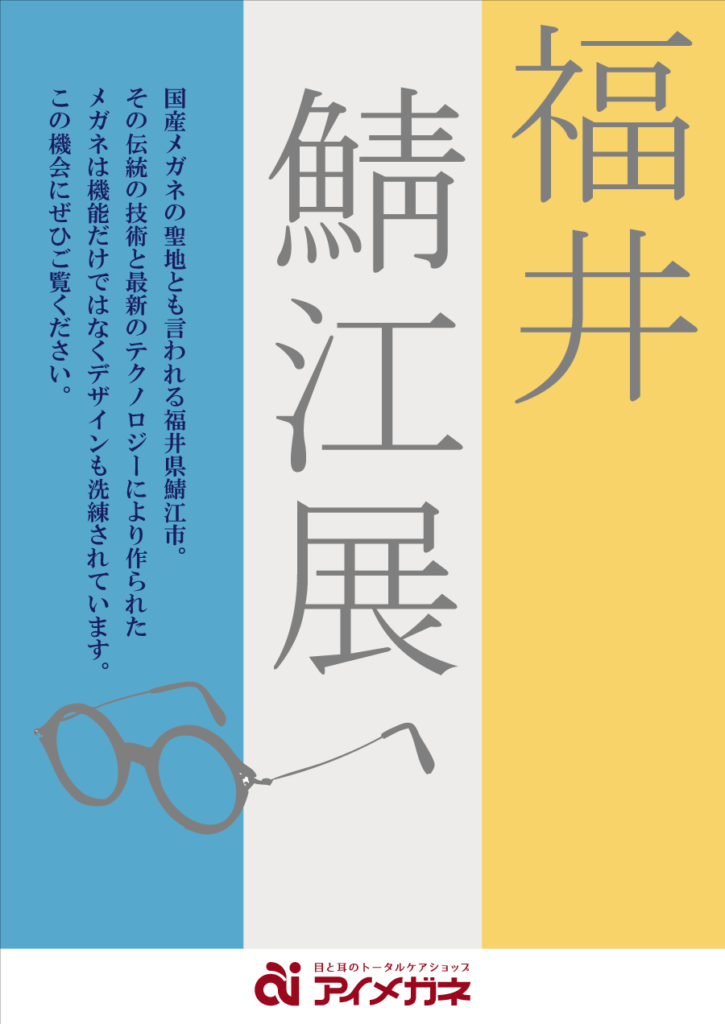
詳しくはアイメガネホームページをご確認ください。
【記事監修】 アイジャパン株式会社 マーケティング本部コミュニケーションデザイン部 木村幸生


